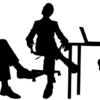本ページにはプロモーションが含まれています。
仕事をしながら介護をしている
ビジネスケアラーが増えている
日常的に大人に代わって病身の親や祖父母、あるいは幼い兄弟の世話をしている「ヤングケアラー」と呼ばれる子どもたちとともに、最近は「ビジネスケアラー」のことが話題にのぼるようになっています。
ビジネスケアラーとは、仕事をしながら家族等の介護をしている人のこと。経済産業省は、第一次ベビーブーム(1947~1949年)に生まれた、いわゆる団塊の世代が75歳以上の後期高齢者になる2025年以降は、ビジネスケアラーの数が優に300万人を超え、日本経済は大損失を免れない、と推測しています。
この推測の背景には、「高齢になった親を在宅で介護するためには仕事を辞めなくてはならないのではないか」とか、「介護のために仕事をある程度セーブしなくてはならないのではないか」といった思いが根強くあるように思います。
しかし私たちの国には、介護保険をはじめとして、介護が必要な方を社会全体で支えていくための公的サービスが各種用意されています。それらのサービスを上手に活用すれば、在宅で老親を介護するために仕事を辞めなくてもいい、つまり「仕事と介護の両立」はさほど難しい話ではないことを書いておきたいと思います。
介護保険に用意されている
日帰りサービスの活用を
退院支援を専門に行っている病院の看護師さんにうかがうと、入院していた高齢の患者さんが退院して自宅に戻ることになったとき、多くのご家族が「日中ひとりにしておけないから、今の仕事を続けるのは無理だろう」と考えるようです。
そんな話が出たときは、もちろん患者さんの状態にもよるのですが、在宅療養に移行しても日中ずっと自宅にいるわけではないという話をすると言います。
平日であれば、介護保険に用意されている日帰りサービスの「デイサービス(通所介護)」や「デイケア」と呼ばれる「通所リハビリテーション」を利用することができます。
いずれも原則として送迎サービスつきですから、ご家族が送り迎えをする必要はありません。自宅で見送ってから出勤し、いつもどおり勤務を続けている方も少なくないそうです。
認知症の方のためのデイサービス、デイケアも
このタイプのデイサービスやデイケアは認知症の方も利用できることを「介護の疲れをデイサービス・デイケアで癒す」で紹介しています、あわせてご覧ください。
通所が無理な方は
各種訪問サービスの活用を
患者さんによっては、知らない人と一緒の時間を過ごすことを嫌い、デイサービスやデイケアに通いたがらない方もいるでしょう。
あるいは床ずれがあるとか、酸素吸入などの医療的な処置が必要、といった理由から、デイサービスやデイケアに出掛けられない方もいるでしょう。
その場合は、訪問看護や訪問介護、訪問リハビリテーションといった訪問サービスを利用すれば、日中の時間帯の介護を専門家に委ねることもできるでしょう。
たとえば訪問看護について言えば、「原則として1日1回、1回の訪問時間は30~90分程度、週に3回まで」といった利用制限があります。
しかし患者さんの状態によっては、この枠を超えて「週に4日以上、かつ1日3回まで」訪問看護を利用できる仕組みも用意されています。詳しくはこちらをご覧ください。
まずは病院の退院支援看護師か
医療ソーシャルワーカーに相談を
いずれにしても在宅介護を始めようというときは、患者さんが入院中であれば、まずはその病院の、退院に向けた支援を専門に行っている「退院支援看護師」や「医療ソーシャルワーカー(通称、MSW)」に相談されるのが一番です。
このうち退院支援看護師は、患者さん個々の健康状態を踏まえ、ご自分でできることや手助けが必要なこと等をよく理解していますから、在宅で必要な医療処置やケア・介護の方法について相談されるといいと思います。
一方の医療ソーシャルワーカーは、社会福祉面で支える専門家です。在宅介護にかかる費用のことも含め、暮らし全般の相談に乗ってもらえます。詳細を知りたい方は「退院や医療費の相談は医療ソーシャルワーカーに」をご覧ください。
地域包括支援センターに
気軽に相談を
入院している病院に退院支援看護師や医療ソーシャルワーカーがいない場合、あるいは諸事情から彼らには相談しにくいとこともあるでしょう。そんなときの相談先としては、「地域包括支援センター」があります。
地域包括支援センターは、地域に暮らす高齢者やご家族の医療・介護・福祉に関するありとあらゆる相談や悩みに各種領域の専門スタッフが対応して、情報提供やサービスの紹介を無料で行う公的な相談機関です。
地域包括支援センターは、原則として市区町村に最低一つは設置されていて、「高齢者あんしん相談センター」などの愛称で活動しているところもあります。
厚生労働省の公式ホームページに「全国の地域包括支援センターの一覧」*¹がありますから、最寄り(離れて住んでいる方は高齢者の居住地)の支援センターに電話、またはFAXや手紙で問い合わせてみるといいでしょう。
あるいは、高齢者のお住まいの市区町村の公式ホームページで探すか、「地域包括支援センター 〇〇市(区・町・村)」と、お住まいの市区町村名でネット検索すれば、所在地や連絡先がすぐにわかります。
介護離職を防ぐために知っておきたいことをまとめた『仕事は辞めない!働く×介護 両立の教科書』(日経BP)もとても参考になります。
「要介護認定」の申請は入院中に
なお、デイケアなどの通所サービスや訪問介護のような訪問サービスなどの介護保険サービスを利用するには、事前に「要介護認定」の審査を受ける必要があります。
退院した当日から介護保険サービスを利用するためには、入院中に要介護認定の申請を済ましておくことをお勧めします。詳しくはこちらを。
「退院前カンファレンス」に参加する
加えて、退院が決まると、入院中の病院側のスタッフと退院後の在宅療養にかかわることになる地域の在宅スタッフとが一堂に会して「退院前カンファレンス」が開かれます。
このカンファレンスには、原則として患者さんやご家族も参加できることになっています。退院後の生活をイメージしたときに不安に思うことや希望があれば、スタッフに伝えて対策を検討する場として活用されることをお勧めします。。
参考資料*¹:厚生労働省「全国の地域包括支援センターの一覧」