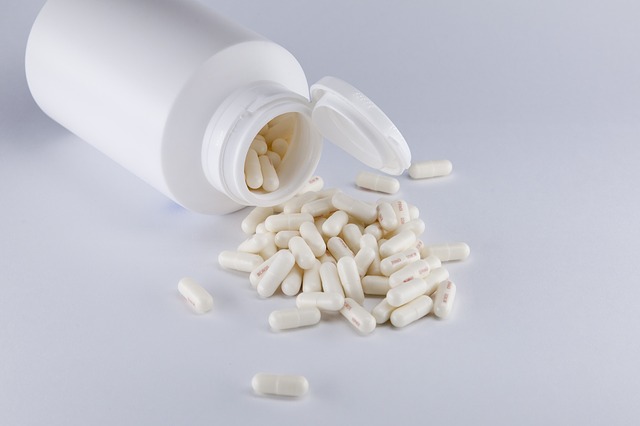本ページにはプロモーションが含まれています。
酸化マグネシウム製剤の
服用者に注意喚起
酸化マグネシウムを主成分とする薬、いわゆる「酸化マグネシウム製剤」は1950年代から、便秘薬、あるいは胃炎や胃・十二指腸潰瘍等の制酸薬(胃酸を中和させて症状を和らげる薬)などとして広く利用されています。
特に数ある便秘薬のなかで酸化マグネシウム製剤が主成分のものは、作用がとてもマイルドなことから、安心して使える便秘薬として愛用している方も多いのではないでしょうか。
この酸化マグネシウム製剤について、同製剤を製造・販売する17社*が共同で、「酸化マグネシウム製剤の適正使用に関するお願い」の文書をWebサイトにて公開し、医療現場に注意を喚起しています。
そしてこの文書には、患者指導用リーフレットとして、「酸化マグネシウム製剤を服用中の患者さん・ご家族の方へ」*¹も掲載され、服用上の留意点が明記されています。今回はそのポイントを紹介したいと思います。
協和化学工業株式会社、株式会社グラフィコ、健栄製薬株式会社、小堺製薬株式会社、株式会社三恵薬品、シオエ製薬株式会社、東海製薬株式会社、東洋製薬化成株式会社、日医工株式会社、日興製薬株式会社、ニプロ株式会社、日本ジェネリック株式会社、マイラン製薬株式会社、丸石製薬株式会社、持田製薬株式会社、山善製薬株式会社、吉田製薬株式会社
長引く頑固な便秘と
マグネシウムの関係は?
リーフレットの内容を紹介する前に、便秘、とりわけ長引く頑固な便秘にマグネシウムがどう関係しているのか、という話をちょっとだけ……。
ご承知のように、水分不足は便秘を招く主因の一つです。水分が足りない状態が続くと、腸管内に留まっている食物残渣、つまり便は固くなりますから、出にくくなります。その状態のまま便が腸管内に長く留まっていると、便はさらに硬さを増すという負の連鎖に陥り、長引く頑固な便秘、慢性便秘に悩まされることになります。
この状態を防ぐうえで、マグネシウムが不可欠なのです。というのは、マグネシウムには、水分を吸収する作用があるからです。
この作用を活かして、マグネシウムをたっぷりの水分と一緒にとると、腸管の浸透圧も働き、溜っている便に水分を与えて便を膨らまし、かつ量を増やして軟らかくして、排便をスムーズにしてくれるのです。
マグネシウム不足と便秘
便秘に関しては日本で初めてのガイドライン『慢性便秘症診療ガイドライン』が2017年にまとめられています。このガイドラインの第5章で、慢性便秘の治療薬としてまず奨励しているのは、マグネシウムの作用を活用した「【第3類医薬品】酸化マグネシウムE便秘薬 」 のような酸化マグネシウム製剤です。
なお、日本人の便秘には、食生活の欧米化によりマグネシウムの摂取量が減少していることが大きく影響しているとも考えられています。薬だけに頼ることなく、豆腐や納豆といった大豆製品やひじき、こんぶなどの海産物など、マグネシウムを多く含む食品を意識的に摂取することも心がけたいものです。
ただ、長引く便秘のなかにはすぐに受診する必要のある便秘もあることをお忘れなく。詳しくはこちらで書いていますので参考にしてください。
酸化マグネシウム製剤と
高マグネシウム血症
酸化マグネシウム製剤の便秘薬は、国内だけで延べにして年間約5000万人に使われているそうです。腎機能が正常に機能していることが条件になりますが、決められた用量を守ってさえいれば、深刻な副作用に見舞われることなく安心して飲むことができるとされています。
ただ、指示どおり服用していても、ごくまれに、「高マグネシウム血症」という副作用に見舞われるリスクがあります。この副作用により死亡、または重篤な状態に陥り、人工透析(血液透析)により一命をとりとめた事例が報告されているようです。
気をつけたい高マグネシウム血症のサイン
そこで今回、2015年に続き、2回目の、「酸化マグネシウム製剤を服用中の患者さん・ご家族の方へ」というリーフレットを発出するに至ったようです。
そこでは、酸化マグネシウム製剤を服用中は吐き気や立ちくらみなどに注意すること。吐き気や立ちくらみの症状を自覚した場合は、「高マグネシウム血症」のサイン*と考え、直ちに薬の服用を中止し、服用している薬を持参してかかりつけ医、あるいは最寄りの医療機関(胃腸内科、消化器内科、一般内科)を受診するよう促しています。
吐き気、嘔吐(おうと;吐くこと)、立ちくらみ、めまい、脈が遅くなる、皮膚が赤くなる、力が入りにくくなる、からだがだるい、傾眠(けいみん;眠気でぼんやりする、ウトウトする)
高齢者、腎臓病患者は
高マグネシウム血症に要注意
酸化マグネシウム製剤の服用により高マグネシウム血症を起こしやすいため慎重に服用する必要がある患者として、リーフレットは以下をあげています。
⑴ この製剤を長期間服用し続けている患者
⑵ 腎臓に病気のある患者
⑶ 高齢の患者
⑷ 便秘症の患者
このうち特に「4」の便秘症の患者については、腎機能が正常であっても、また服用している量が通常の用量以下であっても、高マグネシウム血症を起こすリスクがあるとして、ことさら強く注意を促しています。
血清マグネシウム濃度の検査値確認を
その注意点として、医療機関に向けた文書では、患者に酸化マグネシウム製剤を処方している際には、以下の3点を徹底して実施するよう要請しています。
⑴ 定期的に血清マグネシウム(Mg)濃度を測定する
⑵ 漫然とした処方を避け、必要最小限にとどめる
⑶ 服用中に高マグネシウム血症のサインを自覚した際には、直ちに服薬を中止し、その旨連絡、あるいは受診するよう患者に指導しておく
このうち「1」の血清マグネシウム濃度は血液検査で調べることになります。この値の正常範囲(基準値)は1.8~2.6㎎/dlとされていて、上限である2.6㎎/dlを超えた状態が高マグネシウム血症です。
具体的な目安として「適正使用に関するお願い」では、この値が4.9㎎/dL以上になると、吐き気や嘔吐といった高マグネシウム血症のサインが現れるとしています。これらの症状は、通常、服薬を中止するだけでほとんどが軽快・回復します。重症の場合でも、適切な対応により完全に回復しますから、早めに受診することです。
酸化マグネシウム製剤服用中は、血液検査の結果について自らしっかり確認し、高マグネシウム血症の予防や早期発見につなげるようにしたいものです。
薬に頼る前にシンバイオティクスを試してみる
最近は、排便コントロールにシンバイオティクスを取り入れる方法が注目を集めています。機能性表示食品の「ヤクルト400W 」はその代表ですが、食事によりシンバイオティクス効果をあげる方法もあります。詳しくはこちらを読んでみてください。
長引く便秘が認知症リスクを高める
なお、長引く便秘は認知症の発症リスクを高めていることが、国立がん研究センターの調査により明らかにされています。
脳腸相関、つまり脳の働きと腸の働きが相互に密接に関係し合っているということですが、詳しくはこちらを参照の上、便秘が長引いている方は、早めに受診して便秘問題をクリアされることをお勧めします。
参考資料*¹:「酸化マグネシウム製剤を服用中の患者さん・ご家族の方へ